ここでは、わたしのこれまでどんな音楽を聴いてきたのか述べたいと思う。
そんなこと書いて、誰が喜ぶのだと言うかもしれない。
誰のためでもない。自分のために書くのだ。
黒猫のタンゴ
わたしの生涯の中で、生まれてから最初に、印象に残っている音楽といえば、「黒猫のタンゴ」という曲である。幼稚園の学芸会でダンスをさせられた時の、先生による選曲がこの曲であった。ダンスで黒いタイツを履かされるのも嫌だったが、悲しいメロディの曲であると感じたことが、さらに嫌々感を加速させた。
なぜ、この曲は悲しく聞こえるのだろうか?と疑問に思った。
そこで今回、この記事を書くにあたり、調(調性、キー)を調べることにした。暗い響きの曲であるから短調ということは想像ついたが、ロ短調(Bm)であることが分かった。
ロ短調は、孤独感や受難、哀愁といった「黒いトーン」の表現に効果的な調とのことだ。
ロ短調でクラシック音楽の代表曲は、
・チャイコフスキー
「白鳥の湖」 情景
・ロドリーゴ
アランフェス協奏曲 第2楽章
であるという。ああ、なるほどだなぁと頷いた。
驚いたことに、この曲はずっと日本の曲だと思っていたが、実はイタリアの曲であるという。
原題は「Volevo un gatto nero」で、”nero”という単語が気になった。”ネロ”で思いつくのは「フランダースの犬」の主人公の名前か、悪名高きローマ帝国第5代皇帝の名前である。
しかし、以外にもnero(ネーロ)とはイタリア語で「黒」のことだった。
初耳だ。知っているイタリア語は、「ドレミファソラシド」か「カンパネラ」ぐらいだから仕方がない。
gatto neroとは黒猫(形容詞と名詞の語順が英語と逆?)、曲中のbianco(ビアンコ)は白のことで、「黒猫(gatto nero)が欲しかったのに、君がくれたのは白猫(gatto bianco)だった。」という意味の歌詞らしい。
何だ「タンゴ」という言葉は全然でてこないじゃないか!? 日本語版での「タンゴ」部分は原曲では「ネーロ」と歌っている。日本語版の歌詞は独自に作詞したものだった。
だんご3兄弟
子供の頃からしばらく経ち、この曲の事を忘れかけていたが、ある時、また思い出した。それは、1999年、「だんご3兄弟」が大ヒットした時で、何かの曲に似ているなと思い出したのがこの「黒猫のタンゴ」であった。
似てはいるが、やはり「黒猫のタンゴ」の方が悲しく聞こえるのは自分だけだろうか?
およげたいやきくん
子供時代に聞いた曲で、次に心に残っている曲は「およげたいやきくん」で、言わずと知れた日本一売れたシングル曲(2025年現在)である。小学生低学年時、春の園遊会ではなく、ひなまつりの際、学校でみんなと鯛焼きを食べながら聞いた記憶がある。
子供ながらに、なんて悲しい歌なのだと思った。「黒猫のタンゴ」も悲しい曲だが、「およげたいやきくん」ははるかに悲しい。なぜなら、こちらはメロディーだけでなく歌詞も悲しく、自由を求めて海に飛び込んだが、最後は釣られて食べられてしまうからだ。(と同時に、たいやきは海に入ったら体が溶けてなくなるのではないかと素朴な疑問が湧いた。)
付け加えると、「およげたいやきくん」以上に、見込み違いの契約ミスで、多額の印税をもらい損ねたこの曲の歌い手である子門真人はもっと悲しいだろうが…。
特撮・アニメの曲
子供だから、やはり一番よく聞くのは特撮・アニメの曲である。
帰ってきたウルトラマン
ウルトラマンシリーズのOP曲では、「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」が人気であるが、個人的にはこの曲。何といっても作曲者が「ドラゴンクエスト」のすぎやまこういち!
秘密戦隊ゴレンジャー
オープニング(OP)曲だと思われがちだが、エンディング(ED)曲。「バンバラバンバン…」というフレーズが癖になり、これがなければこの曲の魅力が半減しまう不思議な曲。
作曲者の渡辺宙明が、一通り完成した曲に、レコード会社の無茶ぶりにより、あとでスキャットのフレーズとして追加したようだ。
宇宙戦艦ヤマト
OP曲が有名だが、1作目のED曲「真っ赤なスカーフ」はアニメソング バラード部門 史上第1位ではないか。
【作曲者】宮川 泰
・恋のバカンス(ザ・ピーナッツ)
・ウンジャラゲ(ハナ肇とクレージーキャッツ)
銀河鉄道999
ゴダイゴの映画用版の方がヒットしたが、個人的にはこちらの方がいい。
【作曲者】平尾昌晃
・よこはま・たそがれ(五木ひろし)
・瀬戸の花嫁(小柳ルミ子)
・カナダからの手紙
その他、いろいろあるがあまりにも長くなるのでここで止めておく。
テレビの音楽番組での曲
「ザ・ベストテン」、「夜のヒットスタジオ」を観ていた。親と姉が観ていたからで、自分から積極的に観ていたわけではない。傍観者であったけれども、耳から入った曲は自然と覚えてはいる(もちろん曲しだいだが)。
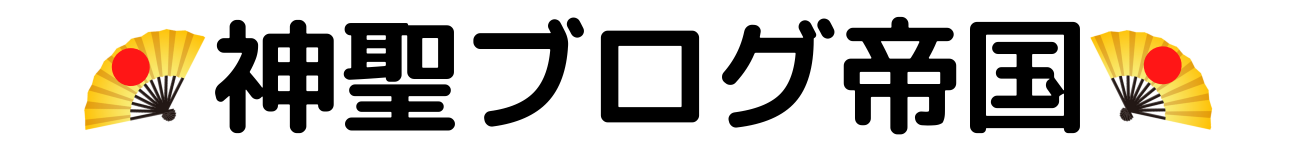



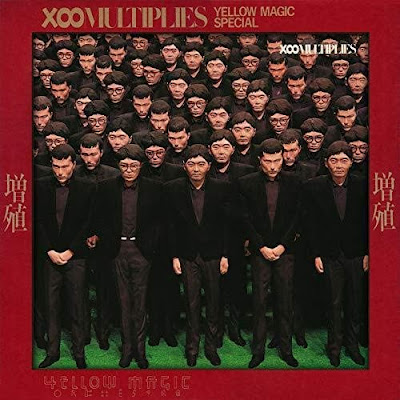

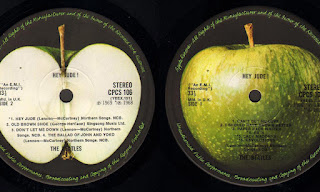









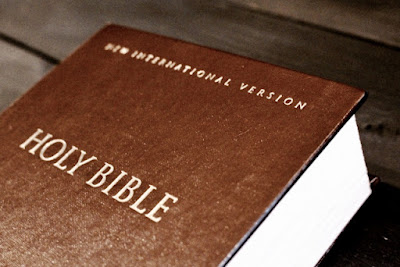



コメント